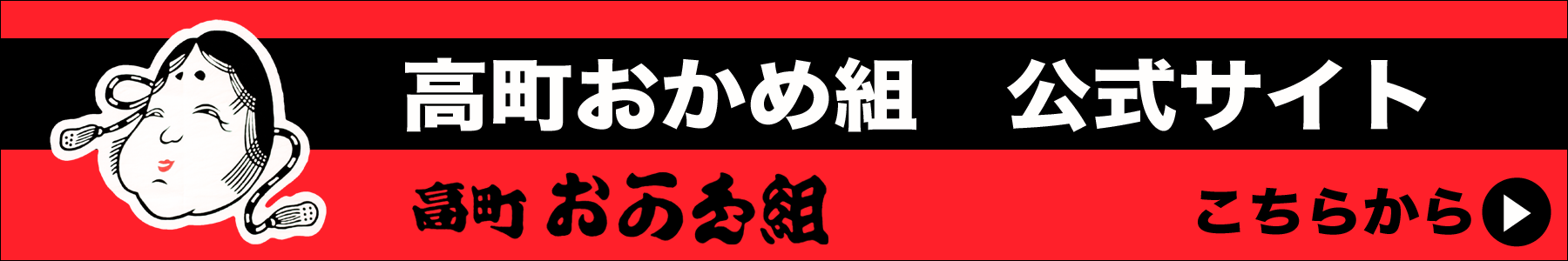高町自治会災害発生時行動マニュアル
【目的】
震度5強以上の地震が発生した場合、町内各自宅内で人命の危険を及ぼす「逃げ遅れ」、「家具転倒等による負傷」などを早期に発見するとともに負傷者の救出、救護、自宅被災者等の町内一時避難所、中部学園避難所の運営及び被害状況の把握と行政への連絡について規定する。
【行動】
◆自治会役員、自主防災隊隊員は自身や家族の安全の確保を行った後速やかに指定された場所に集合し協力して以下の職務を遂行する。
◆町民は、自身や家族の安全確認が確認でき次第、「無事確認黄色タオル」を掲出する。共助のできる方は、緊急避難場所に向かい班長又は副班長の指示に従う。
※防災訓練時にもこの行動マニュアルに基づいて行動するものとする
◆防災本部
本部長(自治会長(又は自主防災隊長))及び本部要員((副自治会長(各班担当の副自治会長は除く)及び自主防災隊役員は以下の職務を遂行する。
1. 本部長は高町公民館(高町公民館が被災の場合は高町ふれあい広場)に防災本部を設置し、統括する。
2.各班長から報告を受けた被災状況を取りまとめ一時避難所の開設依頼及び行政へ被災状況連絡及び中部学園の開設状況を確認する。
3.各班の自主防災隊隊員と連携し一時避難所に必要物資を供給する。
※必要物資は防災倉庫にあるリストにて確認
4.公設避難所である中部学園が開設されたら一時避難所から町民を誘導する
5.中部学園の避難所運営に自主防災隊員と共に従事する。
◆班長 ※班長とは、災害発生時に町内の1班、2班、3班を取り纏めるリーダーで副自治会長等がこれにあたる
1. 1 班、2 班、3 班担当の副自治会長は、各緊急避難場所に集合し各班長としての職務を遂行する。
2. 緊急避難場所に集合した部長、組長、防災委員及び自主防災隊員を指揮する。
3. 自主防災隊員等と協力して防災倉庫に保管してある備品を取り出して以下の準備を行う。
1) 組別安否確認用紙、筆記用具等を準備する。
2) ヘルメット、ヘッドライト・懐中電灯(夜間の場合)、救出用具(バール・ハンマー等)、デジタル無線機、拡声器を取り出す。
3) デジタル無線機、携帯電話を使用して本部長に到着の連絡をとる。
4.自主防災隊他緊急避難場所に集合した2~3人のチームで住民に「無事確認黄色タオル」の掲出を拡声器を使用してアナウンスする。
5.各組の組長・防災委員に各組の安否確認用紙・筆記用具及びビブス(各組名を記入した)を渡し安否確認依頼をする。
6.各組の安否確認及び被災状況をデジタル無線機により本部に報告をする。
7.救出が必要な世帯、安否確認をとれない世帯に対しては自主防災隊員等に救出及びその確認指示を行う。
※掲示板を用いて全般が把握できるように記入を行う
8.緊急避難場所に集まった人を掌握し、以下の指示を行う。
・自宅で生活ができる方 ⇒ 自宅へ(在宅避難)帰宅してもらう
・自宅が被災し自宅で ⇒ 高町一時避難所へ誘導する生活が困難な方
9.怪我人が出た場合、消防署等へ連絡をすると共に町内スキル保有者に救護を依頼する
◆副班長
1.部長、自主防災隊班長は副班長として班長を補佐する。
2.副班長の職務は、以下部長、自主防災隊の項に記す。
◆部長
1.各班の緊急避難場所に集合し、班長の指示を受ける。
2. 班長が被災等により不在の場合は、この職務を代行する。
3. 各組の安否確認及び被災状況を取り纏め班長へ報告する。
4.救出・救護が必要な場合には、スキル保有者・自主防災隊委員と共にこれを行う。
5. 自宅が被災された町民を一時避難所へ誘導する
◆組長・防災委員
※防災委員とは、災害発生時各組の組長と共に以下の防災活動にあたる。
各組で 1 名選出し、任期は 1 年とする、但し再任を妨げない。
1.各組の組長・防災委員は所属する班の緊急避難場所に集合し、各班の防災倉庫に保管してある自組の「安否確認シート」及び「ビブス」「筆記用具」を受領する。
2.自分の組の各戸を廻り以下のことを行う、この時自組の安否確認シートに状況を記録する。他の組長及び防災委員が被災等で不在の場合は、他の組と連携し、相互に補う。
・「無事確認黄色タオル」を掲出した世帯については「安否確認シート」に記録する。
・「無事確認黄色タオル」を掲出していない世帯については、被災されている可能性が高いので状況を確認する。
※r声掛けは、2 次災害の恐れがあるので玄関先で行い家の中には入らないこと
・この際救出などの対応が必要と判断した時には声掛けを行った後で一時、緊急避難場所に戻り自主防災隊隊員等廻りの方の応援を得て、必要な救出機材を持ち救出に向かう。
※決して一人では行わず、複数人で行うこと
・「安否確認シート」に「災害発生時避難行動要支援者」と指定されている世帯については、「無事確認黄色タオル」掲出有無にかかわらず声掛け確認を実施する。
・声掛けの際、自宅が被災された方に対しては安全確保の上緊急避難所へ引率する。
◆自主防災隊隊員
1.自身の所属する班の防災倉庫に集合する。
2.防災倉庫から救出・救護に必要な機材を取り出し(2班は、安否確認に必要な安否確認用紙及びビブス(各組名を記入した)、事務用品を防災倉庫から搬送)緊急避難場所に準備する。この際、火災発生のおそれがある場合には可搬ポンプの準備もしておく。
3.各組の組長より救出の要請があった場合には、複数人で必要機材を持って出向く。
4.火災発生があった場合には、可搬ポンプで初期消火を実施するが、救出を優先する。
5.自宅が被災された方が緊急避難場所に集まってきたら一時避難所に引率する。
6.高町ふれあい広場にある備蓄品倉庫から避難所用備蓄品(トイレ・ラジオ・毛布・シェラフ・カンテラライト等)を一時避難所に運ぶ。
7.各班の自主防災隊班長は、デジタル無線機を使用して班ごとの隊員の調整も実施する。
8.本部からの要請を受けた場合には、本部へ人員の派遣も実施する。
9.中部学園避難所の運営に各町の自主防災隊と共にあたる。
◆町民
1.玄関扉・窓等外から見やすい位置に「無事確認黄色タオル」を掲出する。
2.自宅が被災して自宅での生活が困難な場合は、組長等と複数人で安全確保の上緊急避難場所に向かう。
3.共助のできる方は、緊急避難場所に向かい班長の指示に従う。
◆スキル保有者
1.災害発生時に保有スキルの活用を依頼されている方は、所属する各班の緊急避難場所に向かい必要な救出・救護を実施する。
2.一時避難所で必要なスキルを保有している方は、避難所での生活をサポートする。
◆中部学園避難所との連絡員
1.中部学園避難所との連絡員に指定されている方は、所属する各班の緊急避難場所に集合する。
2.防災本部からの指示で中部学園に出向き避難所開設の状況を逐次デジタル無線機等を使用して本部に連絡をとる。
1. この規約は令和4年 11 月 16 日から暫定施行する
2. この規約は令和 5 年4月 15 日に正式施行した。